こんにちは、田中です。
借金をして賃貸不動産を買えば節税になるって、聞いたことはありますでしょうか。
これって、実は半分ホントで、半分ウソなんです。これは正しく理解しないと危険な誤解になる可能性があります。

節税になる「仕組み」は本当にあるのか?
【1】所得税・住民税の節税:ほぼホント
借金して賃貸不動産を購入すると、経費計上できる主なところは以下のとおりです。
仮に、不動産所得が赤字だとしても、他の所得と相殺(=損益通算)することができます。
例えば、会社員の年収1,000万円の場合、不動産所得がマイナス200万円であれば、課税所得はおよそ800万円になります。この点だけを見れば、確かに節税効果はあると言えます。
【2】相続税の節税:一部ホント・一部ウソ
これは理論上は確かに相続税の節税になると言えますが、以下のような注意点があります。
【3】譲渡所得税(売却時)の節税:むしろ逆、課税が増えることも
つまり、今の所得税は節税できても、将来の譲渡所得税が大きくなることもあります。
結論
「節税になるから借金して不動産を買う」という発想は、目的と手段を逆にとらえているとも言えます。
補足
【1】不動産所得を意図的に赤字(=損益通算)にすることができ、他の所得と相殺できる
確かに「合法的な節税」として一部では活用されていますが、本業の収益を不動産の“赤字”でごまかしているという側面があるため、持続的な資産形成にはされてないと言えます。なぜなら、たとえ税金が減っても、結局、赤字=お金が出ていっている状態であることは変わりはないからです。
【2】節税だけが目的だと、収益性のない不動産を遺すことになると相続人が困る
不動産投資は、①入口 ②期中の損益 ③出口 3つを分析することで効率を読み解くことができます。
つまり、賃貸不動産投資を考えるとき、不確定要素(将来の売却価格や所有期間など)も加味してシュミレーションした結果、プラスの利回りがでると判断ができるのであればGOなのです。仮に、プラスと判断ができない投資であれば行うべきではありません。
【3】相続時の「債務控除」≠「借入金利」 の意味
債務控除とは、相続税を計算する際に、被相続人の「借金や未払い金」を相続財産からマイナスできる制度のことです。
たとえば、
この事例では、「借金そのものの元本」が債務控除の対象です。金利は控除の対象ではありません。
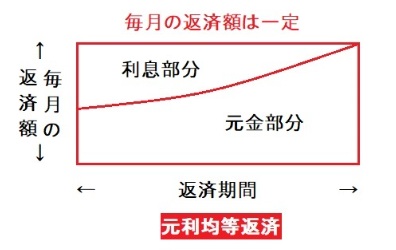
ローンの金利(利息)は、相続税の計算上、債務控除の対象にはなりません。ただし、既に発生している未払いの利息(未払利息)は、一定条件のもとで債務控除の対象になり得ます。
未払いの利息(未払利息)とは?
【債務控除OKな未払い利息の例】
まとめ
アパート建築などでローンを組んだ場合
→ 借入金利は経費(不動産所得の必要経費)として毎年計上できる
→ 元金返済分は経費にはならない
そして、
相続が発生した時
→ 借入元金の残高(ローン残債)は「債務控除」の対象になる
→ 借入金利の扱いは一定の場合のみ債務控除の対象
「ローンが残ってる=全額債務控除できる」と思いがちですが、そう単純じゃないのが相続税の世界です。特に相続税は「発生していない将来の支出」は控除対象外という原則が厳格ですので注意が必要です。
仮に、ローン残債が残っているアパートを相続した人がどうするか?と言えば、元金部分は「債務控除」で相続税が軽減されますが、ローンの金利利息は、相続人が自分の財布から払う必要があるのです。つまり、税金の計算ではムシされるけど、現実の出費はあるという二重構造なってしまうのです。
「借金してアパート建てたら節税になると思ってたのに・・・とならないように慎重なご判断を。
ご来店予約と、メールでのご質問もこちらから
不動産査定AIが即査定額をお答えします無料
※かんたんAI査定は物件データベースを元に自動で価格を計算し、ネットで瞬時に査定結果を表示させるシステムです。