こんにちは、田中です。
誰かが亡くなったあとに必要となる相続手続き。
まずは「相続人が誰か」を確定し、次に「どんな財産や負債があるか」を調べなければなりません。

さらに、相続税の申告は相続開始から10か月以内と期限もあり、「思ったより慌ただしくて、何から手をつけていいか分からない…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続手続きをスムーズに進めるために知っておきたい、役立つ制度や実務上のポイントをわかりやすくご紹介します。

相続人を確定するための戸籍収集とは?
相続手続きの最初のステップが、「相続人の確定」です。
これを行うためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍を集める必要があります。
どんな戸籍が必要?
以下のような戸籍書類を時系列に沿ってすべて集めます。
これらをすべて揃えることで、「誰が相続人か」を法的に確認できます。
収集の流れ
※本籍地が変わっていなければ、1通の除籍謄本だけで完了することもあります。
補助資料について
基本的には戸籍だけでOKですが、以下の書類が必要になる場合もあります。
本籍地が不明な場合
戸籍がつながらない場合
本籍地の変更について
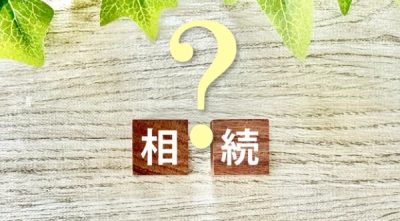
戸籍の広域交付制度(2024年3月施行)
これまで本籍地の役所を順に回り請求していく必要がありましたが、近くの役所で一括取得が可能になりました。
向いている人
注意点
メリット
法定相続情報証明制度(2017年開始)
戸籍謄本等の束の代替として、法務局で認証を受けた「法定相続情報証明書(一覧図の写し)」で各種の相続(不動産の相続登記、銀行・証券・預貯金等)手続きが可能になりました。
向いている人
注意点
メリット

生命保険契約照会制度
相続人等が、「被相続人が生命保険に加入していたかどうか」を把握したいときに有効な手段です。
向いている人
注意点
メリット
名寄帳(固定資産課税台帳)
相続時に、被相続人が所有していた不動産を一覧で確認できる書類です。
注意点
メリット

所有不動産記録証明制度(2026年2月施行予定)
不動産登記名義人(個人または法人)が所有する不動産を、「住所・氏名」などから全国的に一括して調査でき、その結果を「所有不動産記録証明書」として登記所で証明してもらう制度。相続登記の義務化に伴い、名義人の不動産を漏れなく把握するために設けられる。
メリット
注意点
預貯金口座付番制度(口座管理法)
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)に基づき、口座保有者が希望すれば、金融機関でマイナンバー届出をして口座に「付番」が可能。2024年4月1日に施行。

ほふり(証券保管振替機構)
被相続人が株式等を持っていた場合、証券の所在(どの証券会社・どの口座で保管されているか)を把握するのに登録済加入者情報の開示請求をすることができる。発行会社からの株主通知や証券会社の明細と照らし合わせて証券資産の調査に使う。
信用情報機関(CIC / JICC / KSC)
クレジットカード・ローン・割賦払い等の与信・返済・申込・債務整理等の情報を、加盟する金融機関等が信用情報機関に登録・管理し、本人または利害関係者が開示請求できる制度。
自筆証書遺言書保管制度 (2020年7月開始)
被相続人が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)が安全に保管し、紛失や改ざんを防ぐための制度。
向いている人
注意点
メリット
まとめ
相続手続きでは、戸籍や財産、債務、保険などさまざまな情報収集が必要です。制度や方法を上手に活用することで、手間や時間を削減でき、漏れやトラブルを防ぐことが可能です。ただし、新しい制度もあるため、最新情報の確認や専門家への相談も検討しましょう。
ご来店予約と、メールでのご質問もこちらから
不動産査定AIが即査定額をお答えします無料
※かんたんAI査定は物件データベースを元に自動で価格を計算し、ネットで瞬時に査定結果を表示させるシステムです。